Valves' World 番外編その10
811A宍戸式イントラ反転アンプ改修
広島市のFさんから届いたアンプの外観です。
うまくまとめてあり、トランスや真空管も立派なものが使ってあります。
さて、中はどんな具合かなと思って開けてビックリ!
まさに盛りソバがひっくり返った状態、何がどうなっているのやら??
作った本人ももはや覚えていないでしょう。
(ちなみにこれは依頼者ご本人の作ではありません。念のため)
解体する前にとりあえずこのままで特性を測ってみました。
(中を見ているだけに電源投入時はさすがに緊張しました^^;)
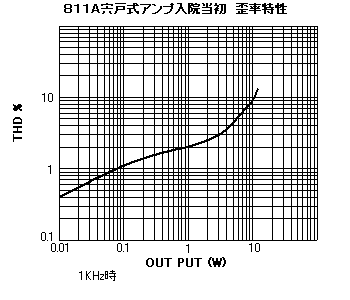
1W出力で既に2%、10Wでは10%に達しています。
おそらく初段やドライバー段の電圧配分の不適切と思われます。
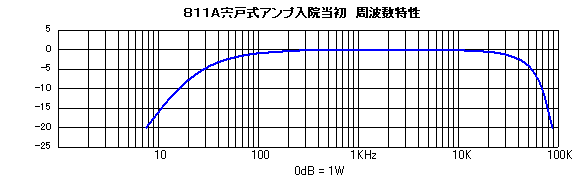
上はともかく、下は200Hzあたりから減衰がはじまり、
20Hzでは−7dBという悲惨な状態です。
くもの巣のような配線を掻き分けて検証してみると、
イントラNC−10が通常通りの結線になっていました。
これではイントラ反転アンプにはなりません。
宍戸先生が折角考案された使用法も、最近は周知されていないようです。
気を取り直して使えそうなパーツを取り出してみましたが、
大量のケミコン類やブリッジダイオードはシャーシにボンドで接着してあり再利用不可、
コンデンサーはこのさい、より長寿命で音質的にも有利なフィルムコンに変更しました。
ドライバートランスNC−10はこのシャーシにはない青いペンキが
付いています。
どこかから外してきた再利用品のようですが、
使い方を間違っていましたのでコアの磁化が心配ですし、
出力トランスも2.5Kが使ってあり、このミスマッチも気になります。
真空管ソケットや端子類それに一部のCR類はは再利用することにしました。
基本回路図
増幅部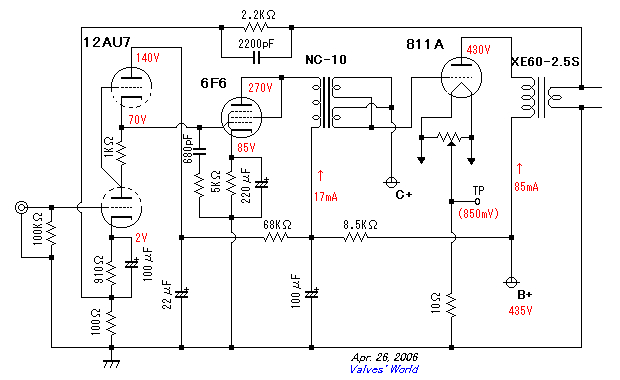
電源部
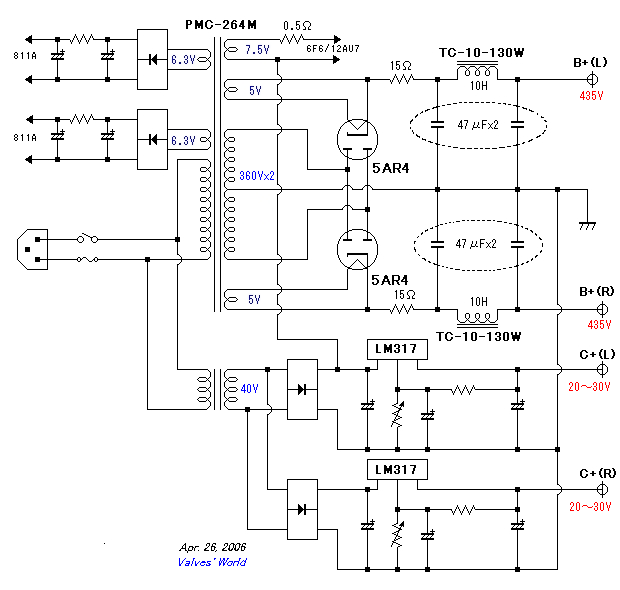
増幅部の回路は宍戸先生のものを忠実になぞったもので、
さらに電源部は整流管以後左右別構成という凝ったものでした。
ただC電源は左右共通になっており、出力管動作を
個別で調節することは
出来ませんでしたので、
この部分だけ左右分離に変更しました。
これは811Aのような本来オーディオ用真空管でない送信管の場合は
その動作点にかなりのバラつきがあり、このアンプのように
固定バイアスで使用するさいはぜひとも必要な措置です。
その他NFB回路は補正が適切になされていなくて、
容量負荷では
高域発振を起こしていましたので補正回路を追加、
それ以外は
折角ですからそのまま引き継いで再組立に進みます。
なお出力トランスは本来最適負荷3.5KΩで、このアンプに使ってあった
XE−60−2.5Sではミスマッチで歪率も相当悪化します。
今回は再利用ということで
やむなく4Ω端子に8Ω負荷、実質5KΩ動作で使用しています。
取り外したトランスなどを並べて依頼者と相談しながらレイアウトを決めます。
レイアウトが決定したところでシャーシの加工と塗装
リフォーム完了写真
正面 シャーシはピアノブラック仕上げ、トランス類はすべて
マットブラックに再塗装してカリン材のウッドケースに収めました。
811Aのソケット周りにはご要望で製作した
化粧リング(かなり苦労しました)をつけました。
いつもどおり入出力端子類は後部上面配置です。
部品配置は左右対称のシンメトリック
後部にはこれもご要望のバイアス電圧、
プレート電流などを
チェックできる端子を装備、
ハムバランサー、バイアス調整VRなども一箇所にまとめてあります。
内部拡大写真は
こちら
改修後の基本性能
出力 13W+13W 所要入力1500mV全高調波歪率 0.5%以下(1W時)
再生周波数帯域 15Hz〜20KHz(−1dB)
ダンピングファクター 2.5
本体サイズ 470Wx330Dx230H
消費電力 185W
測定結果
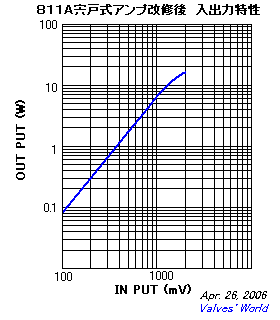
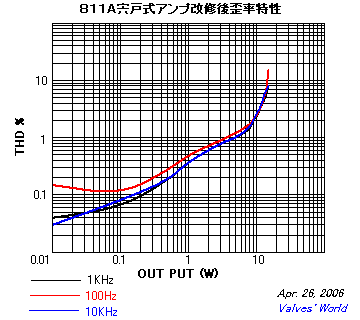
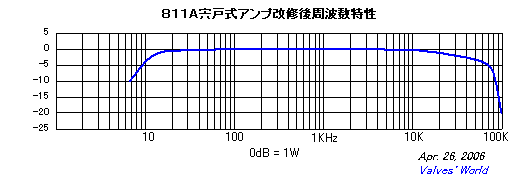
ユーザーレポート
今回のこのアンプは当工房のオリジナル作品ではなく、 単に依頼者のご要望により
個人作品の配線の不具合などを改修、 およびデザインの変更を施したものです。
したがって当アンプの回路に関する他者の特許等には抵触しないものと判断しておりますが、
ご異見等ございましたら直接お申し出ください。
ギャラリー本館へ