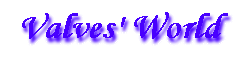
| RCA50 シングル ステレオ |
| 直熱管71Aによるトランスドライブ |
オークションに出品しておりました
このRCA50アンプは
アクセス1500件と
好評の内に終了いたしました。
大勢のご参加どうもありがとうございました。
この場を借りて御礼申し上げます。
以下は出品時の説明文です。
長い間構想を暖めていましたが、受注作品の製作に追われ
完成が延び々になっておりましたが、ようやく出来上がりました。
米国を代表する直熱三極管と言えばあまりにも有名なWE300A/Bが
ありますが、
その前身ともいえるRCA50こそ、知る人ぞ知る
銘球です。
WE300Aの出現に先立つこと5年、1928年に
RCAにより開発された250は
その2年後1930年に252Aとして
改良されWEより発表されました。
その後275Aと発展し33年には
300Aが登場、
当時業務用機器の独占状態にあったWEが
300A/Bをもって、
業界を牛耳ることになり、
RCAは同年民生用として2A3を
送り出しました。
この年には250も現在のST19タイプの
50となっています。
50はグリッド電流が流れやすく通常のCR結合では
動作させることができません。
先人たちはトランスドライブや
ロフチンホワイトなど工夫をかさねて使ってきましたが、
そうまでしても使ってみたい豪快な再生音が魅力の出力管でした。
なお、このアンプでドライバーに使用した71Aは
250のさらに2年前、
1926年にRCAより発売されたラジオ受信機用の終段管で、
その繊細な再生音は今もファンを魅了しています。
今回その50の底力と71Aの繊細さを融合させようと
目論んだアンプですが、
出てきた音はまさに図星、会心の作となりました。
惜しむらくはこの素晴らしいアンプを所有し続けるスペースも
財力もありません。
どうか心あるマニアのもとで繊細かつ豪快な音楽を
奏でて欲しいと思っております。
ご質問、ご相談などありましたら何なりとお申し付けください。
|
使用真空管は初段6C8G、ドライバー71A、出力段50、 整流管は81と6AX5ですべてRCAです。
本体サイズは420x320
|
|
出力トランスはハモンド1628SE、その他はインターステージ
NC-10、電源MX-165、チョークMC-15-150Dと
いづれも旧タンゴ製です。
|
|
高圧整流部にはオイルコンとフィルムコンを採用。
出力端子は8Ωですが簡単な結線替えで4、16オームにも対応できます。
|
|
|
|
ドライバー71A用のフィラメント安定化電源を組み込んだため やや込み合っていますが、他はシンプルな回路構成です。 右のラグ端子はSP出力端子のインピーダンス切り替えジャンパー。 50のソケットには信頼性の高いJhonsonタイプを採用しました。 |
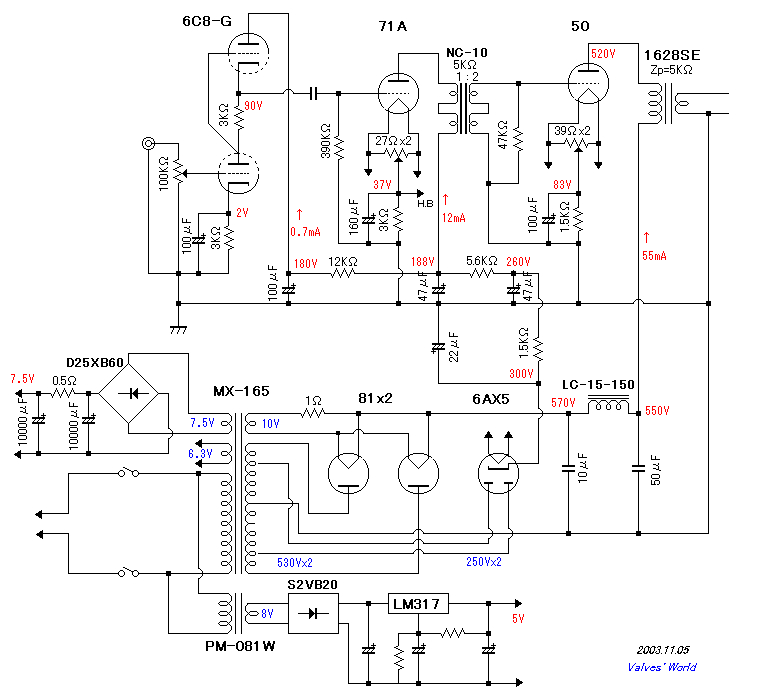
初段は6C8Gで後の6SL7や6SN7などの双三極管の前身ともいえる 球です。
これをSRPPで使用、高域特性の改善と低インピーダンス出力を 実現、次段の71Aにクリーンな信号を強力に送り込みます。
71AはEp180V、Ip12mAと出力管と電圧増幅管の 中間的な動作です。
これでインターステージ2次側に無歪120V以上の 出力が得られ、50を軽々とドライブすることができます。
50はグリッド電流の流れやすい球の代表みたいなものですが、 定石どおりのトランスドライブでその弊害から逃れています。
動作はEp430V、Ip55mAと規格よりやや内輪に抑えています。
電源部は高圧整流部に、かの浅野先生もあまりの整流効率の悪さで 使用を断念した81をあえて採用しました。
50からグリッドを抜いただけのようなそっくりの 姿態ですが、これほど50アンプにピッタリの整流管は、やはり 他にありません。
前段用の電源はトランスにヒーター電源が不足するため 通常はダイオードとするところですが、
カソード・ヒーター間が 高絶縁されている6AX5を使うことにより解決しました。
なお、このヒーター電源には6C8Gの上側ユニットのカソードが 90V前後となるため、
絶縁破壊防止として71Aのバイアス約37Vを 加えています。
測定データ
当工房のアンプはすべて詳細な測定を実施しております。データで音がわかるわけでもありませんし、物理特性を 追求するアンプでもありませんが
お渡しするアンプの 健康状態だけは把握しておきたいと思っています。
入出力特性
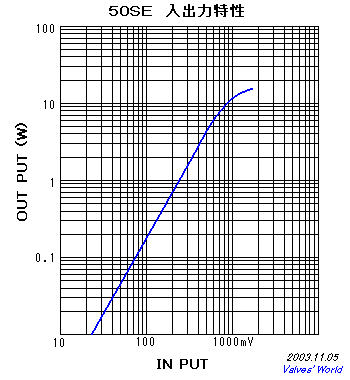
このデータを採って驚いたのは、その凄まじいまでの消化力です。
定格の4.6Wを超えてもどんどんと入力を飲み込んで行き、
飽和しながらもついには3倍の15Wを超えてしまいます。
アンプ作りの先人たちが豪快な球と評した所以がここにあったと、
つくづく思い知らされました。
歪率特性
周波数特性
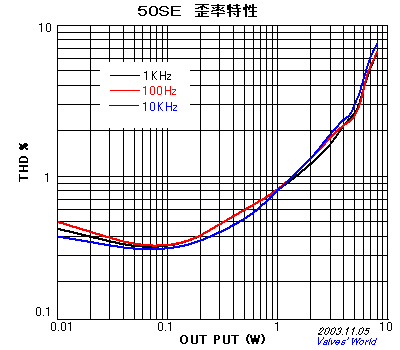
歪率特性も高中低域揃って見事なカーブを描いています。
なお、残留雑音は直熱管ドライブ無帰還アンプとしては
破格の1mV以下を達成しています。
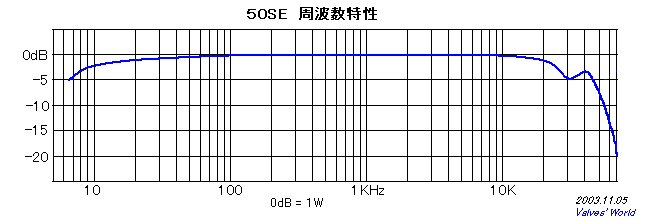
1W時の出力範囲は-1dBで20Hzから20KHzをカバー
しており、NC-10の優秀性が現れています。
40KHz辺りの山は1628SEの特性のようですが、これがこの出力トランスの
音を決めているともいえますし、
NFBアンプではないので弊害も
ありませんからあえて補正はしていません。
ダンピングファクターは可聴帯域内ほぼ2.0でした。
ユーザーレポート
|
ユーザーからのメールによる評価です。 (ご本人の許可を得て掲載しております) |
|
30数年ぶりに自宅で聴くシングルアンプの音だなあと思いま
した。やわらかく、落ち着く音質ですし、聴き飽きがしません
。 大変堅牢なつくりで、常によいアンプづくりの目的意識を持っ てより合理的な構造設計を考えている。また、よいパーツ集め をしていると感じました。良いものを責任持って提供したいと いう気持ちが感じられました。自分のアンプとくらべ水準が高 いので、勉強になりました。シャーシー構造は、参考にさせて いただきたいと思います。 また、シャーシー内部ですが、大きなアースラインとラグ、ソ ケットなどにに合理的にパーツを付けてあり、丁寧な配線をと ともに、合理性を感じました。 現在私は、2A3PP(固定バイアス)で聴いていますが、ボ ーカルがとてもよいと感じられました。 大変良いンプと出会いましたので、長く使いたいと思います。 また、今後良いアンプを出されるのを期待しています。
システム
|
|
以上、福岡市のFさんからのレポートでした。
|